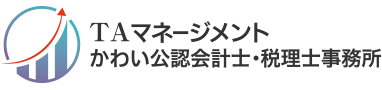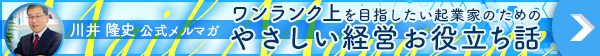「106万円の壁」撤廃よりも深刻——中小企業を直撃する106万の壁解消の本当の狙い

目次
1.動き始めた「壁改革」(改悪)——その本当の狙いはどこにあるのか
パート・アルバイトの働き方を左右する「106万円の壁」「130万円の壁」。政府・厚生労働省は2026年10月をめどに“壁改革”を進めています。多くの報道では「106万円の壁が撤廃される」一方で「パートも社会保険に加入」といった見出しが並びますが、実はこの表現には誤解があると思っています。
今回の改正方針の狙いは、「130万円の壁をなくすこと」ではなく、「週20時間労働の壁」に付け替え、「106万円の壁を実質的にすべての中小企業に広げること」にあるとみています。つまり、「賃金基準(8.8万円)」ではなく「企業規模要件(従業員数51人以上)」を段階的に引き下げ、最終的に11人以上、あるいはそれ以下の事業所にまで適用を拡大していく、この流れこそ、厚労省が描く“静かな全員加入化”のシナリオと思っています。
(注;あくまで106万の壁撤廃と週20時間基準の拡大は現状の方針であり、今後政治の動向などで大きく可能性のあることは申し添えます)
2.改正の本質——「130万円の壁撤廃」ではなく「実質的106万円の壁の拡大」
(1)106万円の壁は「撤廃」ではなく「週20時間の壁に」
現在、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するには、次の要件があります。
- 週20時間以上勤務
- 月収8.8万円以上(年収約106万円)
- 勤務先が「従業員51人以上」の企業(2024年10月以降)
政府はこれをさらに引き下げ、将来的には例えば「従業員11人以上」など、中小企業にも対象を広げる方向で検討を進めています。つまり「106万円の壁」は表面的になくなりますが「週20時間の壁」が、“すべての働き手がその壁に直面する時代”になるということです。
たとえば、時給1,100円・週20時間(月80時間)働くと月収88,000円、全国平均の最低賃金を考えれば、多くのパートはすでにこのラインを超え、106万の壁はそもそもいりません。従業員数要件がさらに引き下げられれば、地方の小規模スーパー、飲食店、保育園などもすべて対象となり、社会保険加入義務がほぼ全国規模で発生するといえます。
(2)130万円の壁は“当面維持”の方針
一方、「130万円の壁」(配偶者の扶養から外れる基準)については、現時点では恒久的廃止の方針は私の知る限り示されていません。政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」で一時的な扶養維持策(事業主証明制度)を導入しましたが、これはあくまで“緩和措置”です。
むしろ今後は、「週20時間の壁」の適用対象を拡大しながら、130万円の壁は形式的に残すという二層構造が続く可能性が高いと私はみています。その結果、社会保険加入義務を負う短時間労働者が一気に増え、企業の負担は“局所的な制度改正”の域を超える規模に達します。
(3)経営現場への実質的インパクト
週20時間の壁を越えたばかりの従業員を抱えた企業側の社会保険料負担は、加入者1人あたり年間およそ16万円(本人負担と同額)と試算できます。従業員50人規模の飲食・小売業であれば、単純計算で年間約800万円の負担増です。
しかもこれは人件費総額の増加に加え、給与計算や労務手続きの負荷増も伴います。
さらに、手取り減を嫌うパート層が労働時間を抑制すれば、人手不足が再燃する可能性も高い。つまり、106万円の壁拡大は「労働供給減少」と「企業負担増」が同時に起きる、二重の構造的ショックを意味します。
3.構造的課題——専業主婦モデルより先に直すべき歪み
社会保険制度の前提は、いまだに「夫が正社員・妻が扶養内パート」という“専業主婦モデル”にあります。この構造を見直す方向性そのものは正しいと思います。しかし、その前に是正すべき、より根本的な問題があります。それが、世代間の負担と給付の不均衡です。
現在の制度では、現役世代から高齢世代への所得移転が極端に大きく、今回の週20時間の壁による適用拡大で新たに保険料を支払うパート層や若年層は、実質的に“払い損”になる可能性が高いです。
ざっくりとした試算ではありますが、50歳のパート主婦が壁を超えると年間16万円の負担増です。それを現状の年金がもらえる65歳まで15年間続けても、年金受取額の増加は年間8.5万円程度、約19年生き続かねば元は取れず、これでは「負担の納得感」は得られません。
しかも、その15年間企業も社会保険を負担しているのにそれは現在の年金受給者に実質的に回されています。専業主婦モデルの見直しは必要だと思いますが、現状の世代間の不公平を解消しないまま制度を拡大すれば、社会保険制度そのものの信頼が揺らぐでしょう。私は順序が誤っていると思っています。
(このあたりの議論は、以下のブログ主の方が丁寧に解説されており非常に参考になります。
【千年安心】の年金に向けて日本は厚生年金を廃止せよ – 新宿会計士の政治経済評論
4.経営層への示唆——“壁のない社会”をどう迎えるか
経営層・管理職として今考えるべきは、「制度が変わる」ことそのものではなく、
“社会保険が企業経営の必須コストになる”という現実をどう受け止めるかです。
対策の方向性は次の3つです。
- 人件費シミュレーションの早期実施
週20時間の壁拡大による将来の企業負担を定量化し、利益計画・採用方針を見直す。 - パートの社会保険加入を“人材戦略”ととらえる
「保険料=コスト」ではなく、「定着・スキル蓄積への投資」と位置づけることで、
慢性的な人手不足解消に活かす。 - 制度改革の本質を見極める
「130万円の壁がなくなるか」よりも、「中小企業まで広がる週20時間の壁」がもたらす 経営構造変化を冷静に捉える。
終わりに
“106万円の壁の“撤廃”とは名ばかりで、実態は「適用拡大による社会保険の全面化」です。
専業主婦モデルの修正は避けられないとしても、世代間の不公平を正さずに拡大を進めるのは、制度の持続性を損なう危険な順序です。
しかし、あなたの会社ではこれにしっかりと適応しなければなりません。“壁のない社会”に向けた人件費構造と雇用設計を、もう描き始めていますか?