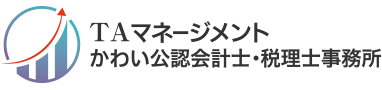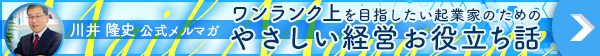「103万円の壁」は本当に消えたのか?令和7年度改正の核心と“見えない壁”を解く
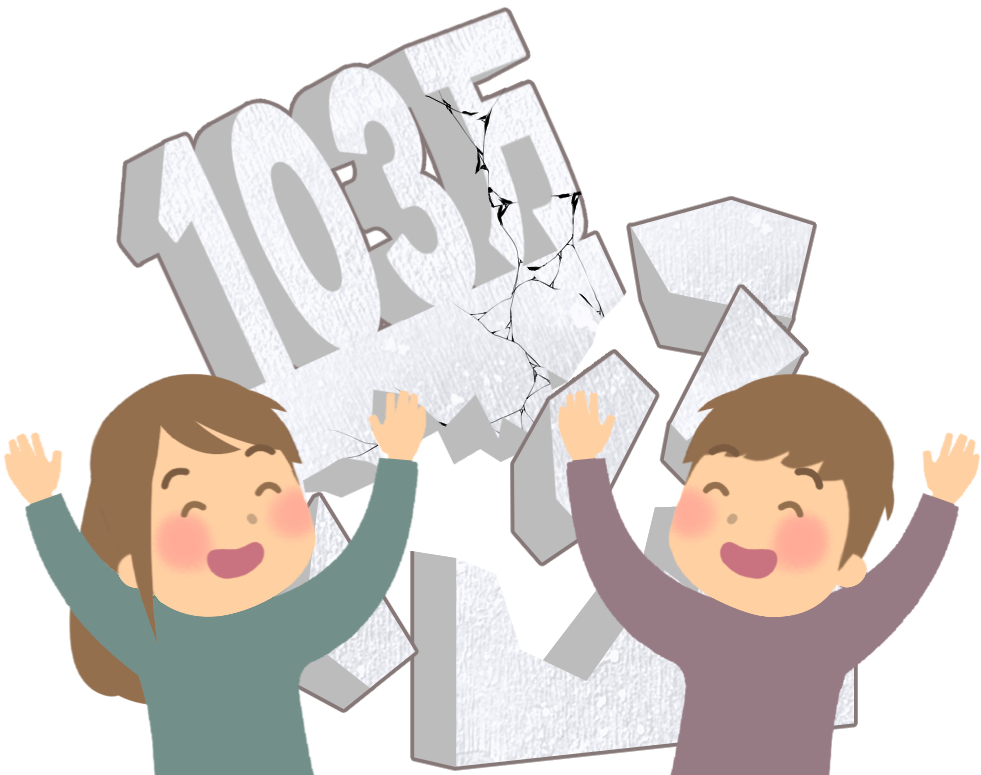
目次
1.『103万円の壁』って何?なぜ問題だったのか?
昔からパートで働く主婦(主夫)たちの間では、「年収103万円を超えないようにしよう」という暗黙の了解がありました。「103万円の壁」とは、年収が103万円を1円でも超えると所得税がかかり始めるラインのことです。どうして103万円かというと、給与収入から給与所得控除55万円と基礎控除48万円(どちらも所得から差し引ける控除)を引くとちょうど課税所得が0円になる年収が103万円だからです。
つまりパート収入が103万円以内なら所得税ゼロ、103万円を超えると超えた分に約5%の所得税が課税される仕組みでした。しかし、この数字は1995年以来ずっと据え置かれてきました。その間に最低賃金は上がり 、物価も生活費も大きく上昇しました。それでも税制だけが昔のままだったため、パートで働く配偶者は「これ以上働くと損かも…」と心配して収入を抑えがちになり、特に年末近くなると勤務日数を減らす現象が起きていました。
本人も収入を増やせない、お店や会社側から見ると、人手不足なのに「103万円の壁」のせいで勤務シフトを増やせないということで、社会問題にもなっていたのです。
2.結局令和7年度税制改正で何がどう変わった?
2025年(令和7年度)の税制改正では、この古い「壁」を現代に合わせて見直す検討が行われました。しかし、すったもんだの末、小出しの減税の上、結局税理士でも間違いそうな複雑なわかりにくいモノになりました。
税制改正では所得税がかからない年収枠の拡大があり、給与所得控除の最低額を55万円→65万円に、基礎控除を48万円→58万円に引き上げました。その結果、これまで年収103万円超で所得税発生だったのが、年収約122万円までは所得税ゼロになるよう枠が広がります。
そして、加えてここで登場するのが「令和7年と8年の時限措置」である基礎控除の特例、合計所得金額132万まではこの基礎控除が58万→95万となります。その結果年収160万まで所得税がゼロに2年間だけなります。
ここでわかりにくいのはこの基礎控除の特例部分時限措置である上に、所得が増えると逓減していき合計所得金額655万超ではゼロ、20万円所得控除が増えるだけになります(合計所得金額2350万超の高所得層は変わらず)。要するに中所得層については20万円の所得控除が増えただけ、ざっくり年間2~3万の減税だけです。
また、いかにも小出しという感じですが配偶者控除の条件緩和がと扶養控除の見直しが行われました。
配偶者控除の条件緩和ですが配偶者控除や扶養控除の「所得要件」(合計所得金額)の上限が従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられました。簡単に言えば、扶養される配偶者や家族がパートなどで稼げる上限が約10万円分アップしたことになります。配偶者については、年収ベースでは約150万円までは夫(妻)の扶養内として満額の控除が受けられるようになりました。それを少し超えても段階的に減る控除(配偶者特別控除)が適用され、配偶者の年収が約180~200万円までなら一部控除を受けられるように拡充されました。
扶養控除の見直し(子や親の場合)ですが、16歳以上の子どもや扶養親族についても、所得要件が同様に48万円→58万円に緩和されました 。特に大学生年代(19~22歳)のお子さんがいる場合は、その子がアルバイトで103万円を超えて稼いでしまってもすぐに扶養から外れるのではなく、合計所得123万円以下まで段階的に控除を受けられる新制度が導入されています 。例えば大学生の子どもが年収120万円稼いでも、親は一定の扶養控除(満額63万円の控除の一部)を受けられる仕組みです。
たまに忘れたころに大学生の子供がバイトを励みすぎて、税務署から扶養控除分の税金を払えというような通知が来てかなりうざかった思いをされた方もいたかと思いますが、少しこの可能性は減りました。
3.実質的には壁は無くなっていない
今回の改正によって、配偶者のパート収入について国税の心配は大幅に軽減されました。「103万円を超えたら即扶養から外れる?」といった不安は、少なくとも国税上はほぼ解消されたと言えます。高収入の世帯(合計所得1000万円超)を除き、多くの中間層家庭では配偶者が以前より伸び伸びと働ける範囲が広がったようにみえます。しかし、残念ながらこれは大きな勘違いです
住民税の壁(100万円前後)は消えていません。所得税と違い、住民税の税率は原則一律10%(所得割部分)で、加えて多くの自治体で均等割(定額課税)として年数千円がかかります。所得税は課税所得に対し最低税率5%から始まりますが、住民税は所得割だけで10%、均等割と合わせると年収に対して実質1万数千円〜2万円台の税負担になります。実は「住民税の方が実質的に大きな壁になる」でこれは全く解消されていません。
そして、国税などよりはるかに高い壁、社会保険の壁(130万円の壁)では社会保険の扶養条件は変わっていません。夫(妻)の健康保険の被扶養者になれる年収の上限(一般的に130万円、条件により106万円)は従来どおりです。したがって、配偶者が130万円を超えて働く場合は、自身で国民年金や健康保険料を負担する必要が出てきます。この壁を超えると社会保険料は税金とは異なり超えた金額ではなく、全額に対して社会保険郎率が一気にかかり手取りは大きく減ります。この社会保険の壁は引き続き意識する必要があります。
少子高齢化で働き手を増やすという意味でこの制度を導入したのであればきわめて中途半端な内容です。減税で国民の負担を減らすという意図ならば低所得者層を除いてはほぼ影響はなく正直「気休め程度」です。わかりにくいだけの残念な理念なきバラマキというのが正直な感想です。