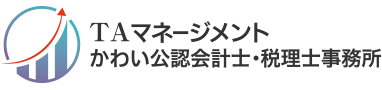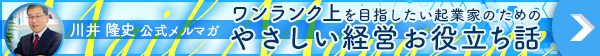前澤氏事件から学ぶ、経営者が陥りやすい“節税の罠

目次
1. 前澤氏の“社債利子スキーム”とは
皆さんも特にネットなどのニュースで取り上げられていたのでご存知かもしれません。ZOZO創業者・前澤友作氏の資産管理会社「グーニーズ」を使った“社債利子スキーム”が、国税局から否認されたという話題を取り上げます。報道によれば、この仕組みによって約3年間で2億円近い利子が経費として計上されていました。形式的には金融取引を装っていますが、実態は「養育費を会社経費に付け替えようとした」構造だったようです。
仕組みは結構他に良い記事がたくさん見つかると思われるので簡潔に説明します。まず、グーニーズが社債を発行し、税理士が関与するコンサル会社がそれを全額購入します。グーニーズはコンサル会社に対して利子を支払い、これを経費として処理します。次に、コンサル会社は自社でも社債を発行し、前澤氏の知人女性(前澤氏の子どもの母親とされる)がそれを購入。その資金は、前澤氏が低利で貸し付けていました。結果的に、グーニーズが支払った利子が迂回して知人女性に流れ込み、彼女は投資のリターンという形で数億円の利子を受け取ったのです。
2. 普通に養育費を払えば良かったのでは?
ここで大事なのは、「養育費として普通に払えば問題はなかったのでは」という点です。養育費は通常、所得税の対象にはなりません。しかし、今回のように数億円規模となれば“生活費の範囲”を超えるものとみなされ、贈与税の対象になると考えられます。贈与税の負担は受け取る女性側に発生し、その税率は非常に高く(最高55%)それもこのケースは一般贈与なので3千万超の部分に適用されるので税金を払えば半分以下になってしまいます、その重さを避けたいという動機が、この複雑なスキームを組む背景にあったのではないかと推測されます。なお、グーニーズ自体は赤字の会社であったため、追徴課税はありませんでした。したがって、法人税の節税効果はむしろ限定的だった可能性が高いでしょう。つまり今回のスキームは「法人税対策」というよりも、「贈与税回避」の色彩が濃いものといえます。すごく好意的に見れば養育費の手取りが大幅に減ってしまうので何とかしたいという前澤氏の優しさが仇となったとも言えます。
国税当局は「伝家の宝刀」といわれる法人税法132条、いわゆる「行為計算否認規定」を適用しました。この規定は「形式が整っていても、実態が課税逃れなら認めない」というもの。要するに、書類や契約で取り繕っても、中身が合理的でなければ否認されるということです。極端な話、国税が認めなければなんでも課税できる規程です。その反面、やはり抜いても納得のいかない納税者と争いになると裁判で負けることもあります。そこで、なかなか抜かない宝刀なのですが今回の件は「抜いた」まさにその典型例でした。
3. 経営者が陥りやすい“節税の罠”
さて、この話は大企業オーナーだけの問題ではありません。中小企業オーナーや個人事業主にとっても、“節税の裏技”は常に身近な誘惑です。代表的なものに「タワーマンション節税」があります。高層マンションの一室を購入し、相続税評価額を不自然に低く見積もることで、実際の市場価値との乖離を利用して相続税を圧縮する手法です。一時期は流行しましたが、国税庁は令和5年に法令解釈通達を出し、こうした不自然な評価を否認し、課税処分を行った事例もあります。形式上は合法に見えても、実態が伴わなければ認められないということです。
そのほかにも、「ペーパーカンパニーを作って経費を膨らませる」「架空のコンサル契約を結んで支出を装う」「必要のない高額の固定資産を購入して償却する」などの提案を耳にしたことがある方もいるでしょう。一見すると賢い手に思えますが、税務調査が入れば簡単に見抜かれます。追徴課税はもちろん、金融機関や取引先からの信用失墜に直結するリスクがあるのです。節税どころか、事業存続を脅かす火種になりかねません。
4. 税理士の本来の役割とは
ここで重要なのは、税理士の姿勢です。本来、税理士の役割は「顧客を守り、長期的な繁栄を支える」ことにあります。ところが一部には「短期的な節税効果」を前面に打ち出し、顧客を引きつける税理士もいます。経営者から見れば頼もしく映るかもしれませんが、実際には顧客をリスクにさらしています。「節税屋」とよばれる業者と組んでの節税スキームは顧客の高いリスクに対して業者のリスクはほぼゼロ、儲かるのは業者です。
税金は確かに重い負担です。だからこそ「節税の魔法」に飛びつきたくなる気持ちは理解できます。しかし、長期的に見れば、健全で持続可能な方法を選ぶことが最も安心できる道です。例えば、「賃上げ促進税制」や「設備投資減税」といった明確に制度で認められた優遇策を活用する。あるいは事業承継の計画を早めに立て、相続税や贈与税の対策を公正に進める。こうした地道な取り組みこそが、将来の安定を守る大きな武器になります。
5. まとめ
前澤氏の事例は、派手で複雑なスキームが実は脆くリスクが高いものであることを示しています。そして税理士にとって大切なのは、「リスクの高い節税を売る職人」ではなく「長期的経営繁栄の伴走者」として顧客を導くことだと思います。短期的な損得よりも、長期的な信頼こそが最も大きな財産になるのではないでしょうか。地味でシケた税理士に思われ方もいらっしゃるかもしれませんが自分はそれはそれでいいかなと個人的に思っています。