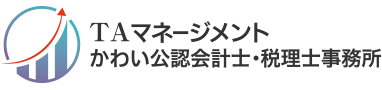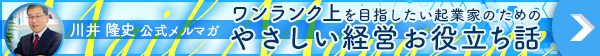恐ろしい往復ビンター社員の横領で会社が“重加算税”!?

目次
1.横領で損害うけた上に税金も?
ある程度の規模の中小企業経営者の皆さん、こんな風に経理を“任せっぱなし”にしていませんか?
- 経理や営業は信頼できる社員に一任している
- 月次のチェックは面倒なのでスキップしがち
- 税理士とは年に一度、決算のときにだけ接点がある
このような運営体制を続けていると、思わぬ“税務リスク”を背負うことがあります。それが「社員の横領」と、それに伴う「課税」+「重加算税の適用」です。
「被害者はうちの会社なのに、なぜ税務署にまで追い詰められるのか?」そう思われる方は多いでしょう。ですが、税務の世界では、社員の横領によって発生した未記帳・過少申告は、「仮装・隠ぺい」に該当する可能性があるのです。つまり「重加算税(本税の最大40%)の対象」となります。
たとえば、経理担当者が売上の一部を着服し、帳簿に反映させずに申告した場合、たとえ経営者がその事実を知らなかったとしても、税務署や裁判所は原則次のように判断します。「帳簿が改ざんされ、納税が適正に行われていない。これは“隠ぺい行為”である」
2.審判所・裁判所の判断は驚くほど厳しい
先日の税務通信の記事にあったのですが、令和6年9月の関東信越国税不服審判所の裁決では、まさに典型的なケースがありました。海上コンテナ輸送を行うX社の営業統括部長Aが、取引先と結託し、支払った運送料の一部を個人口座に受領。これにより法人は本来支出するべきではない金額(部長の懐に入ったお金)を経費として損金計上してしまっていました。
税務調査でこの不正が発覚した結果、
- 横領された金額(個人口座に入金した部分)は損金不算入(=課税所得が増加)
- 同時に、Aに対する損害賠償請求権の額は、「損失が発生した事業年度」に益金算入すべき(発覚した年度でないことに注意)
- 結果として、複数年にわたって申告誤りがあったとされ、重加算税を含む追徴課税を受けた
さらに審判所はこう判断しています。「この不正は、X社自身の行為と同視できる。国税通則法第70条第5項の“偽りその他不正の行為”に該当する」要するに、経営者が知らない従業員がやったことでも、「会社がやったこと」として管理体制が甘ければ“法人としての責任”を問われるということです。加えて、泣きっ面に蜂ともいえるのが損害賠償請求権の益金算入の(要するに利益として認識する)時期です。
3.「損失が発生した事業年度」に益金算入すべき? その理不尽ともいえる厳しさとは
令和6年の不服審判所の裁決では、横領を行った社員に対する「損害賠償請求権」を、損失が実際に発生した年(=横領が行われた年)に益金算入すべきと判断されました。これは実際の現場にとっては理不尽な判断ですよね。
なぜなら――
- 横領の発見などすぐにできない、だから発覚は数年後、それでも「過去の年にさかのぼって益金計上せよ」ということなんです。
会社がその横領に気づいたのは、本人が税務調査で突っ込まれ、自主的に申し出た令和5年。しかし、審判所は「実際に横領が行われたのは数年前なのだから、その年に損害賠償請求権も発生している。だからその年の益金に入れなさい」と言ったのです。
この判断の背景には次のような(杓子定規ともいえる)考え方があります。「損害賠償請求権は、加害者(社員)の行為により損失が発生した時点で成立している」「たとえ発覚が後になったとしても、通常の経営体制が整っていれば把握できたはず」つまり、「気づかなかったのは経営者の責任。だから、損害賠償請求権は遡って計上してね」というのが税務の世界の考え方なのです。
- でも現実的には困難な処理を強いられますよね
中小企業の現場では、数年前の取引内容や金銭の流れを正確に把握すること自体が難しい場合も多いでしょう。にもかかわらず、税務上は「発生ベース」で損益を修正しなければならない。このような状況では、以下のような事務負担が経営者にのしかかります。
- 数年前の会計帳簿の修正(場合によっては再提出)
- その年の法人税等の修正申告、追加納税
- 益金計上によって黒字化し、繰越欠損金の調整や税額変動が発生するケースも
つまり「今、損失が分かったのだから今の年度で処理すればいいでしょ?」という考え方が、税務上は通用しないのです。この判断は、経営者として非常に厳しい現実を突きつけられるものであり、裏を返せば「しっかりとした体制があれば未然に気づけたはず」という内部統制のあり方まで問われる」ということなのです。
重加算税とは、本来納めるべき税金に加えて最大40%が加算される制度です。これに延滞税(年利換算で最大7.3%)も加わると、たとえば500万円の課税漏れで700万円以上の支払いになることもあります。
つまり、被害者なのに、加害者以上の金銭的ダメージを負う」という理不尽な状況も現実に起こり得るのです。このケースでは部長が懐に入れた部分が損金不算入、それに対する損害賠償請求権が益金算入でいわゆる往復ビンタに加え、それに重加算税と利子税が課されるという非常に過酷なものです。
ではどうすればよいのでしょうか?
4.対策はどうしたらよいでしょう
「内部統制」と聞くと、大企業の話のように思えるかもしれません。しかし、中小企業にも実践できる最低限の体制はあります。
・二人以上のチェック体制
経理や入出金の業務を一人に集中させない。「相互けん制」は最も基本的な内部統制です。
・月次で通帳・帳簿の確認
手許現金、銀行残高と帳簿を経営者自身が毎月チェック。数字が苦手でも、明細を“眺めるだけ”で不正の兆候は見つかります。
・税理士との定期面談
申告のときだけでなく、年に数回は会計報告と経営状況をすり合わせる機会を持ちましょう。顧問税理士も単なる税金計算だけでなく、経営管理・監査的な視点を持った姿勢で対処してほしいものです
・ 監査的な目を持つ就業規則と教育
就業規則に「金品の授受禁止」などの規定を明記し、従業員への研修を通じて周知徹底を。
まとめると信頼だけでなく「仕組み」で守る経営を
従業員に経理や営業を任せることは、信頼関係があるからこそできることです。しかし、「信頼していたのに裏切られた」では済まされないのが税務の現実。会社を守るのは、仕組み。横領・重加算税は決して他人事ではありません。まずは自社の体制を見直すことから始めてみましょう。 顧問税理士に「うちはチェック体制、大丈夫ですか?」と一言聞いてみるだけでも、大きな第一歩です。